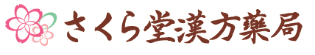逍遙記
二番煎じ
江戸時代
薬といえば草根木皮の煎じ薬という時代のお話です。
当時恐れられていたものの一つが火災。
火災の増える冬には、火消しの人たちが活躍する一方で、
一般庶民も、夜間、「火の用心」の見回りを交代でしていたそうです。
寒い冬の夜のことですが、
見回りの人たちが休憩するための番小屋では、
当番の男衆が、ちょっと一杯、体を温めながら、
ワイワイガヤガヤとやるのがささやかな楽しみだったそうです。
「ところがさ、去年隣町で、酒が入って喧嘩になって、
番小屋での酒は禁止になってしもうた。」
と、楽しみが奪われてしまった町人たちでしたが、ある一人が
「わしは風邪を引いたときには、熱燗を飲むのに限るんじゃ。
医者もそういっておる。
“お前さんにはどんな薬も効かん。熱燗が一番じゃ”とね。
そんでもって、今日はちょっと風邪気味なんで、風邪薬を三合持ってきたんじゃ。」
と酒を忍ばせてもってきました。
それから煎じ薬の口直しと称して酒のつまみも。
その風邪薬を楽しんでいたところに、役人がやってきます。
役人「何じゃそれは」
町人「はい、風邪薬でございます」
役人「何、風邪薬だと。ちょうどよい。拙者も今風邪を引いておるのじゃ。
町人の風邪薬とはどのようなものであるのか、ちょっと拙者にも飲ませてみよ。」
町人は、酒であることがばれたら、打ち首になるかもしれないとおもいながらも、
後には引けず、しぶしぶ差し出します。
役人「何か、風邪薬がすんでおるのう。
ゴクゴクゴク・・・・
なかなか良き風邪薬じゃ。ん~。口直しもよいのう。
もう一杯くれ。」
町人「いや、もうこれでおしまいでございます。」
役人「何。もう煎じ薬がない。
では、よい。
拙者、もう一回り、町内を見回りしてくるから、
二番煎じを出しておけ!」
[南光落語ライブ6 / 三代目桂南光 二番煎じ H12年02月11日 岡山県立美術館ホール]より